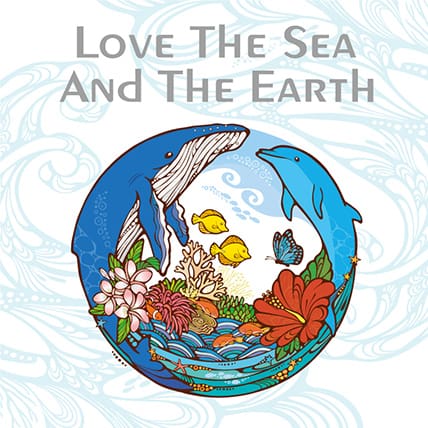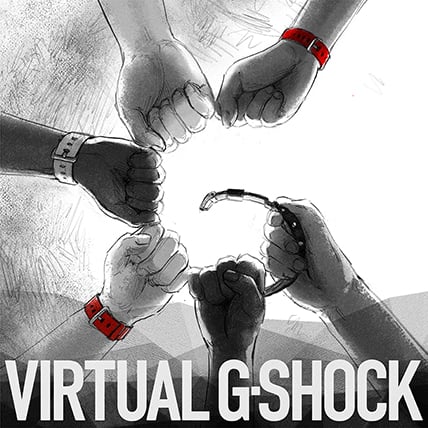Creator Interview
大山エンリコイサム
-Artist-
ストリートから美術史に接続する
クイックターン・ストラクチャー
ストリートアートの枠を超え、
独自の表現を生み出すアーティスト、
大山エンリコイサム。
彼の代名詞である「クイックターン・ストラクチャー」は、
ダイナミックな線と構造美で見る者を
魅了しながら、さまざまな領域を横断する。
今回大山が本誌のために手がけたアートワーク
《FFIGURATI #645》では、
世界的BBOYの
シゲキックスとコラボレーションを実現。
完成した作品に込めたコンセプトを通して、
彼の作品に対する思想を聞いた。


Left / Right
Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #645, 2024
Digital collage, offset printing, paper
15.6 × 23.4 cm each / a pair of two
Artwork ©Enrico Isamu Oyama / EIOS
Breaking ©Shigekix
Photo ©Shu Nakagawa
Interview
縦横無尽の線
重層的な構造
ニューヨークを拠点に活動を続ける大山が、2拠点目として2020年に設立した東京のスタジオ「EIOS Tokyo」で今回の取材を行った。天高6メートルの空間は白い壁で囲まれ、そこにはこれまで制作した作品の痕跡が残されている。その上に制作中のキャンバスが掛けられ、周囲には必要なものだけを選び抜いたツールが整理されていた。この空間は、エアロゾル・ライティングの研究者としても知られる大山の実験室のようだ。
――代表的な作風であるクイックターン・ストラクチャーについて教えてください。どのような影響から生まれたのでしょうか。
高校生の頃に、東京でストリート文化の最初のブームがあり、周りにスケートボードやブレイキンをやっている同級生が多くいました。自分はほかの人と違うことをやりたい感覚と、もともと絵が好きだったこともあり、ストリートアートに興味が向いたんです。そうすると、路上にあるストリートアートが見え始めるんですよね。ライティング(グラフィティ)文化は名前や文字というモチーフも重要ですが、僕はその造形のエレメント、線の躍動感や立体感に惹かれました。そこで文字にこだわらず、むしろそれを取り除いて線の動きのみを反復して、クイックターン・ストラクチャーの原型が生まれました。
――クイックターン・ストラクチャーはどういう原理で動いているのでしょうか。ルールがあれば教えてください。
まずは体の動き、とくに肩や肘を軸にして腕を振り抜くという動きが単位としてあり、それを連ねることでかたちを広げます。次に、そこに平行する線を加えていくと、三次元性のあるストラクチャーになります。それが重なり、連なることで、自由な、流れるような線だけど、同時に構造として設計された形体になる。それが自分の表現の特徴だと思います。
――今回、本誌のためのアートワークを手がけましたが、依頼を受けてから制作まで、どのような考えに至りましたか。
プロダクト本体より、背後にある思想のコアな部分にリーチしたかったんです。カシオ計算機はもともと計算機を作っていて、その流れからG-SHOCKも生み出された。そう考えて、「デジタル」という概念から作品のイメージを広げました。さらに自分はストリートの表現に影響を受けているので、ストリート文化から生まれたアスリートにも関心がありました。そこでG-SHOCKがサポートしているブレイキンのシゲキックスさんとコラボレーションしたいと提案させていただきました。

――具体的にどのようなコンセプトになったのでしょうか。
アートワークは誌面の見開きページに掲載されるので、その構造も活かしたかった。デジタルは2進法の0/1で表現されます。0と1の反復は光の明滅を連想させるので、左右にふたつのヴィジュアルを制作し、その並びが明滅するような表現をしたいと考えました。シゲキックスさんに同じポーズで複数回撮影させてもらい、その時にキャップ、Tシャツ、パンツ、シューズの4アイテムをそれぞれ白黒反転し、そこに自分のクイックターン・ストラクチャーが交差していく。もちろんクイックターン・ストラクチャーも白黒反転させました。デジタルという概念とストリートの文化、視覚表現と身体表現を融合させた作品ができました。
――撮影の現場でディレクションを行っていましたが、シゲキックスさんの動きはいかがでしたか。
完璧にやってくれました。プロのアスリートだからこそできることだと思います。本来ブレイキンは曲に合わせて動くのが特徴ですが、今回は静止画で一瞬を切り取るという試みでした。普段とは異なる、静止した瞬間の、彫刻的な造形を見せられたと思います。それは彼が得意とする「フリーズ」の魅力を引き出すことでもありました。
――これまでも多様なコラボレーションを手がけていますが、それらから得られるのはどういうものでしょうか。
僕にとってコラボレーションはとても大切です。基本的にクイックターン・ストラクチャーは自発的な原理で構成されているので、極論すれば、それ自体で完結できる表現です。そのため、外部にある様々な条件に応答し、クイックターン・ストラクチャーを変化させる必要があります。それは素材や支持体の物理的条件という場合もあれば、他のアーティストやキュレーター、企業とのコミュニケーションやブレインストーミング、もしくは仕事としての要望という場合もあります。そうして、クイックターンが変奏されるのです。今回のアートワーク《FFIGURATI #645》のコンセプトも、今回の座組だからこそ生まれました。そして《FFIGURATI #645》は誌面に掲載する前提で制作しましたが、そこからさらに派生した《FFIGURATI #646》は、明滅のコンセプトをより明確にし、インスタグラムなどのデジタル空間で発表することを前提とした映像作品になっています。そうやって少しずつ、クイックターン・ストラクチャーが内包する造形の可能性を増やしていくことが、僕の活動の可能性も広げていくと捉えています。
01.
アートワーク《FFIGURATI #645》制作のための撮影現場。背景、構図などをすべてディレクションしながら確認、調整を行う大山。シゲキックスのフリーズのポーズも、再現性を考慮しつつ、構想したイメージに近づけるための意見交換を重ねた。
02.
スタジオの一角に作られた撮影スペース。壁に見えるのは、直接キャンバスを貼り付けた状態でクイックターン・ストラクチャーを描き、そのキャンバスを剥がした跡に残る、裏写りした残像のようなイメージ。それが何層にも重なっている壁は、それ自体が作品のようである。

01

02

――大山さんにとってG-SHOCKとはどんな存在ですか。
時計は本来、時間を計るものです。その意味でG-SHOCKは時計以上のものでしょう。現代社会は時間に追われていて、日常は時間を計るツールで溢れていますよね。G-SHOCKはファッション的なアイコン性もありますが、衝撃に強い点でも、ただ時間を計る存在ではなく、多義的で、物理的な存在感を持っている印象があります。
――スタジオで制作に取り組むために、心がけていることを教えてください。
ここで膨大な時間を過ごすので、自分にとって心地よくあってほしいと思っています。僕の場合は、制作時の動線にストレスがないことを意識して、制作プロセスに最適化された空間になっていますね。そう考えるとスタジオの空間は、自分の身体の延長というか、自分の身体がそのまま外側に展開された空間とも言えます。制作中はひとつひとつのアクションで絵の画面がどんどん変わります。たとえば、右上に少し線が加わっただけで構図の力学が変わって、さっきまでよいと思っていた画面が急に落ち着かなくなったりします。足したものを引くことはしないので、もっと足してもう一度バランスを取るのですが、その過程はすごく神経を使いますし、画面を凝視しながらそれを続けていく。その瞬間が一番、夢中になっている時かもしれません。

Profile.
大山エンリコイサム/Enrico Isamu Oyama
美術家。ストリートアートの一領域であるエアロゾル・ライティングのヴィジュアルを再解釈したモティーフ「クイックターン・ストラクチャー」を起点にメディアを横断する表現を展開。イタリア人の父と日本人の母のもと、1983年に東京で生まれ、同地に育つ。2011-12年にアジアン・カルチュラル・カウンシルの招聘でニューヨークに滞在以降、ブルックリンにスタジオを構えて制作。2020年には東京にもスタジオを開設し、現在は二都市で制作を行う。
Left
床にはホワイトのシートが貼られている。「壁も床もすぐに汚れるので」と本人は言うが、その汚れすらアートの断片を見ているようだ。随所に大山の動きの痕跡があり、空間全体にクリエイティブな雰囲気がある。
Right
スタジオ内の備品はすべてブラックに統一され、必要なとき瞬時にアクセスできるように整えられている。ツールワゴンには同じ種類のペンやピンセットがそれぞれ10本前後ある。インタビューで話していた心地よい動線が実現されている。



スタジオ内にあるロフトからの風景。大型のキャンバス作品を制作するための十分なスペースがある。すべての什器にキャスターが付いており、制作する目的に合わせて自由に移動ができる。
THISTIME MAGAZINE
Tokyo Creator's Creative Scene