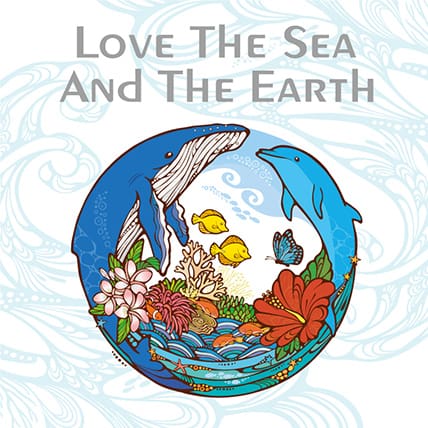Creator Interview
山谷 佑介
-Photographer-
タフネスを持って
挑戦し続ける写真家
写真家、山谷佑介。人々が交錯するライブハウスの床をテーマにした作品から、SNSで参加者を募って撮影した野湯のシリーズ、
さらに自身がドラムを叩けば自動でシャッターが押される仕組みを考案して撮影を行ったヨーロッパツアーなど、
唯一無二なアイディアで我々を魅了し続けている。
そんな彼が夢中になってきた写真とは何か。
G-SHOCK DW-5000Rのために撮りおろした全編モノクロのストーリーとともに、話を聞いた。












Interview
何をしても気にならない
タフなものがベース
2013年に制作した初の写真集『Tsugi no yoru e』で脚光を浴び、その後、京都国際写真祭やNYのコンデナスト本社ビルでの展示など、国内外で活躍を続ける写真家、山谷佑介。常に新しいことにチャレンジし続ける彼の写真は、どのようなマインドから生まれているのか。
―― 山谷さんの作品はテーマごとにそれぞれ全く違う印象なのに、どこか一貫したものがあると感じます。どのようなことを大切に写真と向き合っているのでしょうか。
僕は人物を撮影することも多いのですが、人物撮影が好きなわけではないんです。撮っているのは、人ではなく、そこに起きている現象という感覚。人をしっかり立たせてライティングするスタイルでもないし、大きく捉えればずっと風景のスナップ写真を撮っているイメージです。初期のスナップ写真や『ground』という作品もそうですが、人を撮っているようで、あまり人の顔が写っていなかったり。それは写真を始めた頃から今でも一貫したスタイルかもしれません。
―― 人は社会を構成するほんの一部で、撮るのはそこにある現象ということですね。山谷さんは音楽がバックボーンにあり、ドラムを叩きながら撮影された作品もありますが、それもその現象を切り取ったということでしょうか。
そうですね。15歳でパンクバンドを始めて、ドラムを叩いてきました。『Doors』という作品は、ドラムを僕が叩いたら3台あるカメラが振動を感知して自動的にシャッターが押されるという仕組みを考え、その場でプリンターから出力できるようにしました。カメラが一定のリズムで回転しているので、自分以外の周りの環境やお客さんも含め、その場の瞬間でしか起こりえない写真が撮影されるんですよ。それが面白くて。やっぱり僕は永遠の客観主義者。自分がコントロールした写真はあまり楽しくない。撮ったというより、写っていたというほうが僕にとっては心地よい写真との向き合い方ですね。

大学時代から親交の深い友人が店長を務め、20代から遊び場として過ごしてきたライブハウスWWWでの1枚。背景に写っている写真は彼の作品。事前に撮影した床を原寸大にプリントして貼り付け、音の鳴りはじめから終わりまでを記録したもの。観客の足跡、こぼしたアルコール、染み付いた汗、タバコの灰など、会場の一晩の様子が作品に定着されている。
―― 今回、DW-5000Rをモチーフとして、12ページのストーリーを撮影してもらいました。全編フィルムのモノクロ写真で構成された作品は、どのような想いで制作されたのでしょうか。
これまで生活してきた場所で、リアルに繋がりのある人たちを被写体に、自分なりのG-SHOCKのタフネスを表現しました。そもそも最初に写真にのめり込んだきっかけが、ライアン・マッギンレーやダッシュ・スノーの写真集。身の周りに起きている日常をただただ撮るという手法で、当時衝撃を受けたんです。その影響を受けた初期の頃と近しいイメージで撮影をしました。被写体は、地元の仲間から東京で知り合った友人や先輩、今住んでいる家の隣人にまで声をかけました。年をとるごとに、環境や人付き合いが変わっていくのが普通だと思います。それでもいまだに連絡を取り合って遊ぶ仲間に共通するのが、好きなことをブレずに夢中になってやり続けるタフなマインドを持っていること。隣に住んでいるスケーターでありラッパーの子も撮影させてもらいましたが、彼が友達と遊んでいるのを見ていると、自分の若い頃と重なるし、それが僕にとって刺激になるんです。時間は前にしか進まないけど、人の記憶のなかにある時間は回っている。このストーリーは自分事ではありますが、誰もが過ごしてきた時間を通して、そこにある何かを感じとってくれたら良いなと思います。
―― 撮影する時に使う道具や身につけるものについて基準のようなものはありますか?
今日着ている革ジャンやパンツも、普段乗っている古いパジェロもそうなのですが、どれも汚れても何をしても気にならないタフなものが一貫したベースになっています。カメラは、90年代前後のコンパクトなフィルムカメラを使うことが多いですね。性能はもちろん、当時のものはいい意味でオモチャのようなデザインが多いんですよ。いろんな機能が付いていますが、別に使わなくてもデザインとしていい。でもちょっとイジりたいと思った時に機能が意外と役に立ったりする。そう考えるとG-SHOCKの良さと、自分が選ぶものってすごく近い気がしています。今温泉のシリーズを作っているのですが、山奥に行くのでG-SHOCKは良さそうです。丈夫なのはもちろん、時間を確認するためだけに携帯をポケットから出さなくていいし、タイムスケジュールも組みやすい。日が暮れてしまって遭難する心配もないですから(笑)。撮影する時に、唯一“アリ”な時計です。
―― ずっと写真に夢中になっている理由を改めて教えてください。
写真というメディアが持っている特性が、自分の性格に合っているんだと思います。写真って熱いようで冷めている。どんなに適当に撮ろうが写る。撮る側が無の感情でも「被写体の個性が出て良い写真ですね」、なんて言われたりもする。そのクールさにずっと夢中になっているんだと思います。だからシンプルに時を刻む時計というデバイスは、とても共感を持てます。時間のように淡々と、意味性を持たず、世の中を切り取っていけると楽しいかもですね。

撮影の時は、ほかの何も気にせずタフなものを選ぶという山谷佑介が愛用するジャケットと、写真を始めた初期から使っているフィルムカメラ。今回のストーリーでは、タフな人や街とともに、時のサイクルも切り取った。

Photography. Asuka Ito
Interview & Text. Tatsuya Yamashiro _MASTERPLAN
Edit. Takuya Chiba Satoru Komura _THOUSAND
Profile.
山谷佑介/Yusuke Yamatani
1985年新潟県生まれ。大学卒業後撮影スタジオに勤務。その後、国内を転々と旅し、長崎で出会った東松照明をはじめ、数多くの写真家と交流し、写真を学ぶ。これまでに6冊の写真集を発行し、展示も多数。
Instagram. @yusuke_yamatani
THISTIME MAGAZINE
Tokyo Creator's Creative Scene