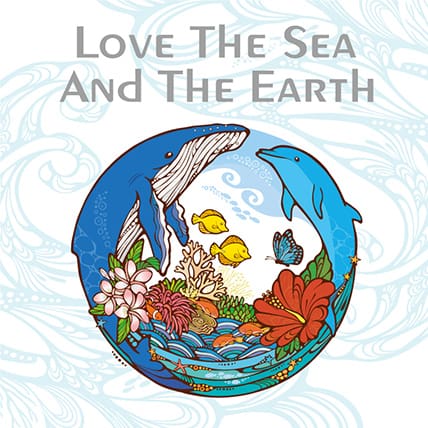チームランドクルーザー・トヨタオートボデー 社員ドライバー三浦昂
考え続ける走りで挑むダカールラリー

「チームランドクルーザー・トヨタオートボデー」は、トヨタ車体が自社で生産を手掛けるトヨタ・ランドクルーザーで「ダカールラリー」に挑戦を続けているチームである。ここに社員ドライバーとして合流している三浦昂選手が、ダカールラリーまでの道のりを語った。
パリ・ダカールラリーは、スタート地点とゴール地点を変えながら長年アフリカ大陸で競技が行われていたが、2009年からは南米、そして2020年からは中東のサウジアラビアへ、とその舞台を移して開催され、その名称は「ダカールラリー」に代わったが、現在も、年末年始に2週間かけて総移動距離1万キロ前後を走行する、世界で最も過酷なラリーレイドとして知られている。
三浦昂(みうら あきら) profile

幼少期からモータースポーツ好きで、就職活動でトヨタ車体がパリダカに参戦していること、そして社員をナビゲーターとして起用していることを知り2005年にトヨタ車体に入社。
社内公募に応募し、2006年の5月に、候補生としてチームに移籍。2007年にナビゲーターとして、リスボンからダカールへ駆け抜けたアフリカ大陸最後の大会となったパリダカに初参戦。
【関連商品はこちら】
その場から逃げ出したかった“初勝利”
三浦選手が現在ダカールラリーで乗り込むのがトヨタ・ランドクルーザー(通称:ランクル)である。チームランドクルーザー・トヨタオートボデー(当時のチーム名はトヨタ・チームアラコ) は1995年からランクル80で参戦を開始。1999年からはその後継モデルとなるランクル100、そして南米に舞台を移して開催された2009年からはランクル200を、2023年からはランクル300を投入と、世代を超えてランクルで挑戦を続けている。

「入社1年目に公募の試験を受けて、2年目にすぐ異動してチームに入ってるんですよ。それってイコール社会人経験無し、じゃないですか。学生がいきなりプロのチームに入って、現場に行ったらスタッフはほとんどプロの契約選手。こっちは、仕事をするってことの意味もわかってないんです。言葉の壁ではなくて、みんなが何を言ってるのほんとうにわからなかったし、何を求められていたのかもわからない。会話とか感覚が僕だけ合ってないっていうことがわかるんですよ。その、孤独感とか恐怖感っていうのが常にありましたね」
ラリー競技ではドライバーだけでなく、その助手席にナビゲーターが乗車する。競技中は、ロードブックを読みながら、ドライバーに走行ルートや走行に関する指示を出し、車両がスタック(動けない状態)した際などには一緒に車両の応急処置を行い競技続行のサポートをする役割を担当する。
長い期間ダカールラリーに参戦をしてきている三浦選手に、一番辛かったラリーはいつのラリーか聞くと、この最初のナビゲーターとしてのデビュー戦の話が出てくる。
「あんまりかっこいい話じゃないですけど、何がなんだかわけわかんないうちに、レース本番が来て、明日こそは、明日こそはって思ってる間にゴールしちゃったんです。2週間は長くも何にも感じなかったんですよ。あぁラリーがもう終わってしまったっていう感覚しかなくて。でも、勝っちゃったんですよね、その時。」
「で、唯一自分の中で確かなこととしてわかるのは、このチームのメンバーってやっぱりみんなプロフェッショナルですごいってこと。でも、この当時20~30人ぐらいなんですけど、その全員がきっちり仕事をしていて、ナビゲーターのシートに座ってる人は僕じゃなくても勝てたんだなっていうことだけがわかりました。本当に何もできなかったんだっていうことを知ってるのに『優勝してどうでしたか?』って聞かれて、それに答えなきゃいけない。もうそれが嫌で嫌でしょうがなくて…。自分の好きなことで今まで味わったことないぐらいの嫌悪感が生まれて、もう“早く逃げ出したい”という思いしかなかったです。」
「だけど、やっぱ好きなことで逃げ出したとしたら、もう僕はこれから何も勝負できないだろうなっていうのもあって、ここでやっぱり実力つけるしかないという思いに至りました。だからある意味そこがスタートラインだったんだと思います。」
三浦選手がトヨタ車体で6人目となる社員ナビゲーターであった。ランクル200のデビュー戦の翌年となる2010年で一度ナビゲーターを降りている。
そして、企業広報の仕事を担当しながら2013年にナビゲーター復帰。さらに2015年には社員のままドライバーに転向、初めてトヨタ車体の社員ドライバーが誕生した。

「正直、会社に入った時には全然ドライバーになるなんてイメージはなくて。それでも割と長く活動が続いていった時に、あるインタビューを受けまして『ドライバーに憧れてモータースポーツの世界に入ったのに、このままでいいんですか?』ということを言われました。で、確かにそうだよなと思ったんです。そんなときにたまたま社内で会社創立70周年を迎えるにあたり、活動提案というか、新しいチャレンジを提案するチャンスが来たんですよ。ほんとたまたまですけれど。それでドライバーに立候補し、なんかこう、とんとん拍子で決まっていったという感じでしたね。」
遅咲きのドライバーの武器は
“とにかく常に考える”、そして自信につなげていく

「ドライバーにチャレンジするっていう挑戦権を得た最初はものすごいテンションが上がりましたが、やっぱりプレッシャーがものすごくて、そのファーストステージのスタートで、クラッチ踏んだらガタガタ足震えちゃって。このままだと最後まで持たないって思いながらスタートしたのは辛かったです。」
「そんな私に、ナビゲーターのローラン(故ローラン・リシトロイシター選手)が『最初からうまくできることなんて何もない。君は今ここまで練習してきて、ここで本番だと思ってるけれども、ダカールラリーの本番が何よりもダカールラリーの練習なんだ。君は今回このステージをひとつ走っていくごとに、他の人にはないくらいの飛躍を見せるはず。だから、そこを見て走れ』って話してくれて、ほんとうに彼には支えられましたね。」
ダカールラリーといってイメージするのは砂丘越えである。目の前にビルの壁のようにそそり立つ砂山を登っていくと、空しか見えない状態になっていく。その砂丘の先がどうなっているのかわからない。断崖絶壁のように何もないかもしれない。だからと言ってそこでアクセルを緩めてしまったら、砂に足を取られスタックしてしまう。スピードを乗せて飛び出すところまできっちりとアクセルを開けていかねばならない。その走りを実現するのは容易なことではない。
ダカールドライバーに必要なものはなにか?という問いに三浦選手は答える。
「やっぱり自分はできるって信じるしかないんですよね。無茶したら死ぬかもしれないと思って乗ってるけど、ギリギリまでいろんなこと考えて、自分はできるっていう確信を持ってやってることなんですね。」
「例えば砂丘で、向こう側はわかんない。どうなる?となっても、とにかく思考し続ける。ラリーだけじゃなくて、全てのことにおいて。そういう感覚ってトップドライバーはみんな持ってるんじゃないかなって思いますね。」
ラリーレイドの難しいポイントの一つにロスト(設定されたコースを見失うこと)がある。いかに速く走行ができても、コースを見失って右往左往するようでは、結果は残せない。
「僕自身がナビゲーターやってたのもあるんで、できるだけ二人で一緒にナビゲーションしてるんですよね。」
「みんながロストしても、僕たちは二人でナビゲーションを考えれるから、いち早く復帰できるっていうのは武器にできるはずだと思ってるんです。」
「もう考え続け、考え続け、延々とやってます。で、そういう難しいところに来て迷ったら、ものすごいロスになってしまいます。だからその手前でタイムを捨ててでもナビゲーションに集中しようとかっていうこともあるし、どっち選ぶかっていうのもずっと考えてます。だから僕は1日のステージが長いって思ったことあんまりないんです。結構考えてるとあっという間に終わっちゃう感じですね、いつも。もうずっと考えて考えて、次の次の次の次の、という具合で。」
三浦選手にとってのダカールラリーとは?

「『過酷ですね』って言われるんですけど、僕にとって1年間で1番幸せな2週間です。クルマの運転のことだけ考えていられるなんて幸せって思ってるんで。」
「次が1番良かったダカールになったらいいなと思って、毎年やってます。そんな中でも、今までのダカールで幸せだと思ったのは、2022年大会、ランクル200のラストランの時ですかね。2015年にランクル200でドライバー・デビューして、自分の技術の未熟さをクルマが助けてくれたんです。ランクルってすごかったんだなっていうのを、身をもって体験したんで、すごい感謝の気持ちが大きかったんですよ。」
「それで、最後の1回ぐらいは、ランクル200のポテンシャルはこれだけあるんだっていうのを全部出してあげたいなっていう気持ちで乗れたんです。とにかくクルマが走りたいように思いっきり走らせてあげたいということを考え続けられたんで、なんかすごくポジティブな気持ちで乗れて、あの年は楽しかったですね。」
そして、2022年大会で、三浦・リシトロイシター組のランクル200はクラス優勝を果たし、まさに有終の美を飾った。
【関連商品はこちら】
ラリーとG-SHOCKの共通点、「本質は変わらない」
復帰した2013年以降は毎年ダカールラリーに参戦。三浦選手はアフリカ、南米、そしてサウジアラビアでの大会を経験している。今のダカールラリーはパリダカじゃないという意見も少なくはない。近年のダカールラリーのこの変化についてどう思っているのだろうか?

「そういうことを言う意味もわかります。今は、以前の冒険的要素よりも、モータースポーツ性が上がってきているように感じますし、求めているのと違うっていう人がいるのもわかります。ただ一方で、長く続くものって、やっぱり本質を変えずに形を変えている。製品にしろ、ブランドにしろ、そういうパターンって多いじゃないですか。体力的にも精神的にも、その究極の状況で選択を迫られるっていうことは、目指すゴールの方向がちょっと違うだけで、今も一緒なのだと思うので、そういう意味では僕は変わってないって受け止めてます。」
「本質という点では、G-SHOCKも同じで、すごい究極を追い求めているんだなと思います。クルマにしても運転にしてもやっぱり究極を求めるんですけど、でも、なかなか簡単には届かない。でもその届かない悔しい思いって次のエネルギーになって、物事だったり考え方だったり進化してくと思うんですけど、G-SHOCKも同じだと思うんです。」
「G-SHOCKについては、当然いいことばっかりじゃなくて、もっとこうだったらっていうようなことをカシオの皆さんに言ったこともあるんですよ。でも「これだけは譲れない」って、なんでも聞いてくれるわけではないんですよ。だからすごく信用できるんです。譲れないものがあるっていうことは、それだけ魂がこもってるということじゃないですか?それってラリーの時も同じで、いくら会社がノーと言っても譲れないことがあるし、そういう意味で仲間意識っていうか、志を同じくする同志みたいな感覚がありますね。」
今回のTLCとの新しいコラボレーションモデルは夜間走行をテーマにして仕上げられている。

「砂漠の夜のイメージはやっぱり『怖い』になるでしょうね。とにかく日没が来る前に砂丘を越えたいって一心で僕らも走ってるんです。とにかく暗い。こっちはヘッドライトしかない。ライトってライトから発する光を反射するものがあるから見えるんです。反射するものがなくなると完全にブラックアウトするんですよ、砂丘を超える瞬間って。」
「その見えないところを越えていく瞬間も思考し続けてるんですが、考える材料がないんで、ここだけイチかバチかになるんですよ。だから、その瞬間だけはやっぱりちょっとドキドキしながら。でも、やっぱりそういうピンチを越えた後って、ちゃんと自信がつくじゃないですか。怖いし嫌だって思うけど、こういう環境が自分を鍛えてくれてんだろうなっていうのは感じますね。」

「今回の夜間走行をテーマにしたコラボモデルって、車内に設置している我々がラリーで使うツールをモチーフにしてるんですよ。だから、僕の中でダカールラリーの感覚がすごく強くて。ダカールラリーで走ってる景色、夜のシーンが浮かんでくるデザインだなって思ってます。これリップサービスとかそういうのでもなくて、歴代コラボモデルの中でこのモデルが1番好きです。」

【関連商品はこちら】
Xプレゼントキャンペーン情報