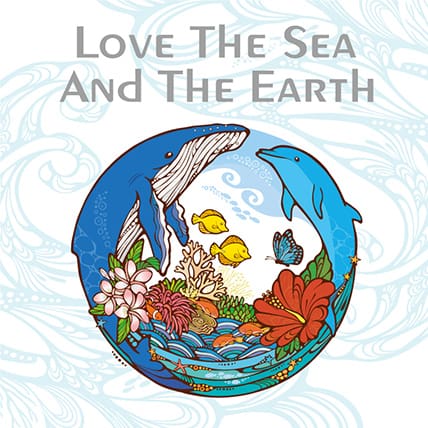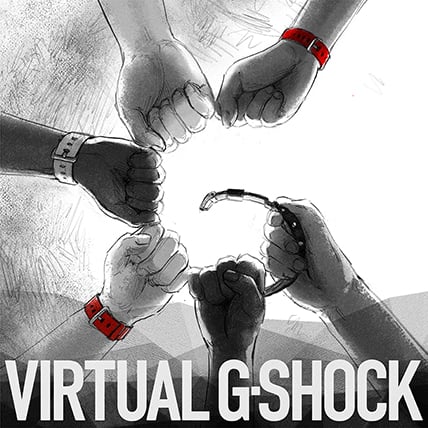絶滅危惧種「カバ」をテーマにした、Earthwatch Japan コラボレーションモデル。
「LOVE THE SEA AND THE EARTH」というテーマのもと、地球環境と生物多様性の保全を行う「Earthwatch Japan」とコラボレーション。絶滅危惧種に指定されているカバをモチーフに、大自然の中でたくましく生きる姿を特別仕様のカラー&デザインで表現しました。ベースモデルは、過酷な環境での使用を想定したMUDMANを採用。環境への配慮として、バイオマスプラスチックやタフソーラーを採用したほか、パッケージに再生紙を使用しています。

G-SHOCKは、1990年代より様々な環境団体とのコラボレーションモデルを制作し、団体のサポートを続けています。

1971年にアメリカ・ボストンにて発足された国際NGO。世界各地で行われている、時間・資金・人手を要する地道な野外調査を、「資金と人手」の両面で支援している。野外調査へのボランティア派遣活動は、世界で最も古く信頼されてきた。独自の厳しい基準に基づき審査・認定した年間100を超える野外調査プロジェクトを支援。200人の国際的研究者と連携しつつ、4000人以上のボランティアを動員するなど、一連のプロセスをきめ細かに管理・運営している。
https://www.earthwatch.jp


野生のカバをイメージした
外装カラー&テクスチャー
カバの体色をイメージしたブラウンとブラックを基調に、分厚くてざらざらした皮膚の質感を表現。ベゼルとバンドを凹凸感のあるテクスチャーデザインに仕上げており、陸生哺乳類として世界で3番目に大きく、タフなカバを連想させます。ボタン周りのメタルパーツには、ローズゴールドIPを採用しています。
カバ
サハラ砂漠以南のアフリカ大陸に生息し、哺乳綱偶蹄目カバ科カバ属に分類される偶蹄類。農地開発や湿地開発による生息地の破壊や水資源の競合、さらには食用や牙用の乱獲・密猟等により個体数が激減しています。IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでVU(危急種)に分類されている絶滅危惧種となっている。


環境保全への思いを込めた
スペシャルデザイン
バンドに、「Earthwatch Japan」のロゴマークと「Change the World. Yourself.」のメッセージをプリント。LEDバックライトを点灯すると、液晶に団体のロゴマークが浮かび上がります。コラボレーションモデルとして、環境保全活動に込められた思いをデザインに落とし込みました。


コラボレーションを飾る
特別仕様
裏蓋に「LOVE THE SEA AND THE EARTH」のシンボルマークを刻印しました。パッケージには再生紙を使用した専用のボックスを採用しています。

素材へのこだわり
バイオマスプラスチック
ケース、ベゼル、バンドの主な樹脂パーツに、環境負荷低減への貢献が期待されるバイオマスプラスチックを使用。
※画像はイメージです。

光を動力に正確な時を刻む
マルチバンド6電波ソーラー

自然の変化を感知する
トリプルセンサー
(方位、気圧/高度、温度計測)
SPECIFICATIONS
• 耐衝撃構造
• 防塵・防泥構造
• 20気圧防水
• タフソーラー
• 標準電波受信機能(マルチバンド6)
• 方位計測機能
• 気圧計測機能
• 高度計測機能
• 温度計測機能
• 日の出・日の入時刻表示
• ワールドタイム(48都市)
• 1/10秒ストップウオッチ
• タイマー
• 時刻アラーム5本
• フルオートLEDバックライト
(スーパーイルミネーター)
Earthwatch Japan 研究者の声
私は主に昆虫の分類学を研究しており、静岡を中心に日本各地で、土壌に生息するハネカクシなどの小型甲虫の分類研究や分布調査をしています。研究対象の種は、自然環境が良好な森林にしか生息しないことも多く、地域ごとの生物多様性の把握や、自然環境保全につながる重要な研究と考えています。調査では南アルプスの高山帯や伊豆諸島・小笠原などにも足を運び、現地の環境を細かく記録しています。
フィールドワークでは、G-SHOCKとEarthwatch Japanのコラボレーションモデルを着用しています。高度計測機能は登山中の現在地把握に役立ち、夜間でもバックライトで視認性が高く、キャンプや山小屋での活動時にも重宝しています。また、アラーム機能は定量的な調査の時間管理にも活用でき、実践的な場面で大きな助けとなっています。
Earthwatchの活動は、研究者だけでなく参加者にも貴重な体験を提供しています。一般の方と一緒に調査を行うことで、新たな興味や発見が生まれ、研究者としても多くの気づきを得ています。企業による自然環境への長期的な支援や、生物多様性保全への取り組みが広がることを願うばかりです。こうした活動を通じて、より多くの方々に自然の奥深さや研究の魅力が伝わることを期待しています。
< プロフィール>
岸本(きしもと) 年郎(としお)
ふじのくに地球環境史ミュージアム 教授
1971年大阪市生まれ。東京農業大学大学院博士後期課程修了。博士(農学)。一般財団法人自然環境研究センター上席研究員を経て、2014年に静岡県職員として現職場に赴任。以後、ふじのくに地球環境史ミュージアムの設立に携わり、2018年より現職。専門は昆虫分類学、生物地理学。日本全国各地で土の中に住む小さな甲虫を追いかけている。また、環境省や地方自治体による外来種対策をはじめとする様々な生物多様性施策立案・実行のための委員などを務め、博物館人として地域に根差した生物多様性の理解と普及を進める活動の推進に尽力する。