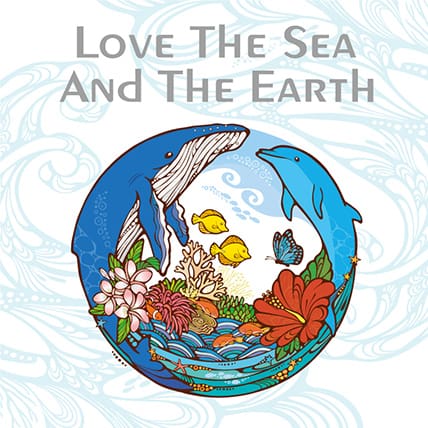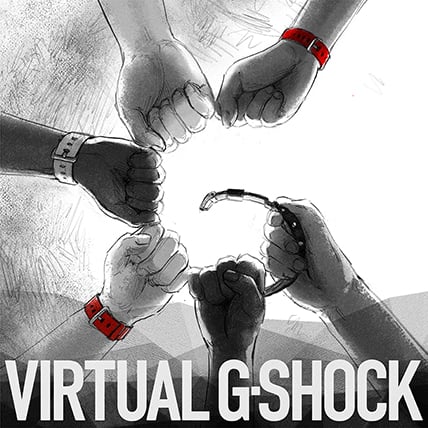時を超える、タフという価値
長い時間をかけて美しく鍛え上げられた日本の絶景や歴史的建造物を通して、「究極のタフネス」というコンセプトで、時計の世界で独自の、しかも不動のポジションを確立しているG-SHOCKの最高峰「MR-G」の魅力を紐解く。
第一回は山形県の東部に位置する石の聖地を取り上げる。
MRG-B2100Bと山寺を結ぶ
悠久の技術と伝統の形
By 後藤繁雄
風土とは、大自然と人の営みを、悠久の時が練り上げ醸成して作り上げていくものだ。
人間は自らの力だけで、歴史を作り上げて来たと思いがちだが、実は風土の働きの掌中にある。日本人の生活様式や思考様式の深層は風土が決めているのだ。
日本の文学批評の神様であり、稀代の目利きであった小林秀雄は、ある時に「伝統とは物なのです。形なのです」と言った。
その言葉には、人の匠の技によって生み出された物や形は、人の生が消えた後に残って初めて伝統になるという冷徹な逆説が込められている。それは、日本の職人技の話だけでなく、あらゆる芸能芸術の根にある、時間に対するタフな姿勢への指摘だ。
G-SHOCKの最高峰であるMR-Gという山形カシオの最先端テクノロジーの精華もまた、この摂理の中にある。山形の月山や最上川の支流が形づくる風土の中に建てられたマザーファクトリーで生産されていることは、意外かもしれないが、私には深く風土の働き、その結縁を感じさせる。
時計は、時をあつかうテクノロジーだ。おまけにG-SHOCKは、40数年前に誕生して以来、「衝撃に耐える」というタフネスの精華を一貫して追求して来た。時をあつかう時計そのものが、時を超える匠を目指すミッションに貫かれてきたことは、なんと興味深いことか。

【垂水遺跡】新第三紀凝灰岩の地層に蜂の巣状に穴が開いた奇岩が霊場に相応しいタフで荘厳な景観を形成する。
そのことで、私が強く連想するのは、ファクトリーから程遠くない山寺にある垂水遺跡・立石寺の絶景の存在である。ここは9世紀に比叡山天台宗の僧、慈覚大師円仁聖人によって開山されたが、垂水の石窟は円仁が最初に来訪のおりに、その地を宿とした伝承もある場所であり、今も強い霊威が感じられる。
いや、広大な立石寺全体が、その名が示すとおり、岩盤の上に出来上がった聖地と言った方がよいだろう。円仁が清和天皇の勅許を得て開いたこの名刹は、比叡山からの不滅の法灯や如法経書写を今も引き継ぐ、時を超えて生き続ける稀有な信仰の場所なのだ。


【垂水遺跡】巨石・巨岩が複雑に入り組み、独特の「神秘的な美」を生み出す。
極論するならば、石による卒塔婆や石塔、石鳥居など、この霊地が生きながらえてきた大きな秘密に石がある。この霊地全体が、古代から継承された、優れた石工たちの技術の賜物であり、いや正確には、自然の力と、それを知る職人の共作なのだ。
水と風が生み出した凝灰岩の断崖に穿たれた、無数の風穴の造形なくして、修行者たちは、彼岸をイメージできなかったろう。まさに自然と人の営みの醸成が、垂水遺跡を時を超えて生き存えさせた。

【立石寺】数百万年から数万年前に形成された百丈岩と呼ばれる断崖絶壁の上に建つ納経堂
はたして、1000年以上の時を超えた遺跡に対面して湧き上がるこのエモーションはなんだろう。人間の生の時間などよりも遥かに長い時間を過ごして来た物たちと、どのような対話が行われるのか。
時は見えない。見えないけれど、これほど人間と切り離せないものはない。人間は不死ではない。だからこそ時を超える物や形を生み出そうとするに違いない。
そこにおいて重要なのは、技術。職人的な技術だ。なかでも、MR-GのMRG-B2100Bが、時計を衝撃から守るベゼルとアウターケースだけで27個の部品で構成されているのを知る時、私は大きな因縁の力の働きを感じるのだ。


【立石寺】悠久の時を経て出来上がった巨岩・奇岩からなる山全体が信仰の場となっている。
未来という時間への技術
現代のアーティストや建築家に大きなインスピレーションを与え続ける文化人類学者ティム・インゴルドが、その著書『メイキング』の中で、鋭く根源的な考察を行っているのを思い出す。
彼いわく。未来について理論家と職人では異なる答えがもどってくるだろうと言うのだ。理論家は、考えることを通してつくる者であり、職人はつくることを通して未来を考えると。
「職人の方法は、周囲の人や事物との観察に基づいた結びつきから、知識が育まれることを許容する。これが、わたしが『探究の技術』と呼んでいる実践である」
彼の提唱する「探究の技術」は、作りながら、次に何が起きるのかを見ながら前に進んでいくやり方だ。垂水遺跡が悠久の時を超えるタフネスを勝ちえたのは、そしてMRG-B2100Bが同じく、時を超えるタフな美しさを物やら形に実現できているのは、まさにインゴルドの言う「探究の技術」に貫かれているからに違いない。
いにしえは、過ぎ去ったものではなく、未来という時を生み出す物であり形なのだということを、山形の風土が生んだ垂水遺跡・立石寺とMRG-B2100Bが、ともに私の中で共鳴しあうのである。
MRG-B2100B
先端素材と匠の技を融合した多パーツ構成の造形美。
日本伝統の美意識を宿した精緻な表情。
後藤繁雄 Shigeo Goto
大阪府生まれ。編集者/クリエイティブディレクター。京都芸術大学教授。80年代より編集者、アートプロデューサーとして時代に一石を投じる数々の企画に携わり、古美術から最先端の現代アートにいたるまで、幅広い活動を行ってきた。なかでもアーティストの才能の発掘・育成には並ぶ者がないほどに精通し、現代の目利きの一人としての定評が高い。主な著書に、『独特老人』(ちくま文庫)、『skmt』(坂本龍一との共著、ちくま文庫)、『超写真論』(篠山紀信との共著、小学館)。最新刊に『現代写真とは何だろう』(ちくま新書)がある。