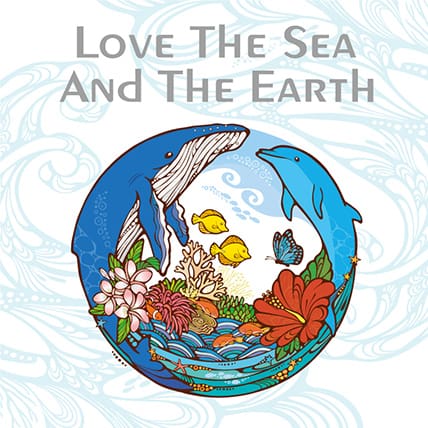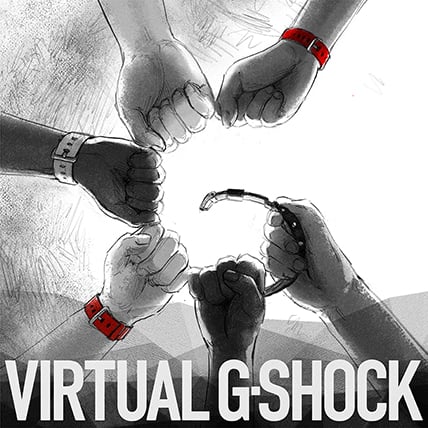伝統の技を受け継ぎながらも決して型にとらわれない美しさと強さの両立
素材、技術、美意識のすべてにこだわったMR-Gに限定500本として、「MRG-B5000HT」が登場しました。ベゼルとバンドに施されたのは、日本古来の鍛金技法「鎚起(ついき)」。この仕上げを手がけたのは、鎚起職人・渡邉和也氏です。ひと打ちに宿る意志、金属に命を吹き込む感性。その真髄とMR-Gとの共鳴について、渡邉氏に話を伺いました。

渡邉 和也(わたなべ かずや)/鎚起職人
1978年、新潟県三条市生まれ。長岡造形大学卒業後、銅器製作の老舗・玉川堂で伝統技術「鎚起(ついき)」を修業。2005年に独立し「鍛工舎」を設立。伝統に根ざしながらも独自の造形を追求し、現代工芸賞ほか受賞多数。現在は個展・様々な分野との協業を中心に活動し、2025年で制作活動20年を迎える。
一枚の金属板を、金鎚で何千何万と打ち込みながら成形していく「鎚起(ついき)」は、日本の金属工芸技法です。主に湯沸かしや茶筒などの器物を生み出してきたこの技法は、継ぎ目のない立体造形を実現するばかりか、打つごとに素材の強度を高めていくのが特徴です。一打一打が、職人と素材の対話。まさに、叩いて起こす、という言葉どおりの表現です。
今回、MR-Gを手掛けた鎚起職人の渡邉和也氏は、新潟県燕市で代々受け継がれる鎚起の伝統を学んだのち、2005年に独立。以来20年にわたり、鍛金をベースにしながらも、アートや建築との接点を模索してきました。
「鎚起ってもともとは道具をつくるための技術なんです。湯沸かしとか茶筒とか、目的がはっきりしている。でも自分はそこからもう一歩踏み出したいという思いがあって。伝統に学びながらも、現代的な造形に挑戦してきました」
その自由なアプローチが、今回のMR-Gとのコラボレーションに繋がりました。

渡邉氏が任されたのは、時計のベゼルへの鎚目加工。素材は、G-SHOCKの最高峰であるMR-Gにふさわしい高性能チタン合金「DAT55G」。鎚起を施す場合によく使用される一般的な銅やステンレススチールはもちろん、一般的な高級時計に使用されているチタン素材と比べても、遥かに硬く、工芸素材としては「限界に近い」と語るほどの超高硬度金属です。
「最初は正直、叩けるかどうかすら不安でした。金属や石材を加工するための工具である、通常の『たがね(鏨)』では歯が立たない。チタンって傷も目立ちやすくて、逆に叩きすぎると歪むなど、力加減ひとつで均一性が損なわれてしまうんです。たがねの研ぎ具合や打つ角度、深さ、どれもミスが許されない精度が求められました」
彼が大切にしたのは、「工芸の感覚」と「工業の精度」をどう融合するかという点。手作業ならではの「揃わなさ」が生む美しさと、時計として成立させるためのミクロ単位の精度。その矛盾のような課題に、渡邉氏はさまざまな試行錯誤を重ねて挑み続けました。

「MR-Gが求める『鎚目』と、自分が普段やっているものとは、ちょっと感覚が違ったんです」
そう語る渡邉氏の挑戦は、試作品の制作から始まりました。理想の鎚目を模索し、完成イメージを共有する。しかし、ひとつとして同じにはならない手作業ゆえに、打ち続けるうちに感覚も微妙に揺らいでいきます。
「やり続けていくと、だんだんわからなくなってくるんです。たがねの刃先は、打てば打つほど少しずつ削れていく。0.1ミリ、0.2ミリと変わっていくと、鎚の音も感触も違ってくるんですよ」

それをコントロールするために、砥石を使って都度たがねを調整し、道具の状態まで意識しながら作業する。求められるのは「均一ではないが、乱れてもいけない」絶妙な表情。鎚目のわずかなずれが、組み上げたときの全体バランスにまで影響してしまうため、常に緊張感を伴う作業です。
「最終的にすべてが組み上がったとき、初めて自分の打った『点』の意味が見えてくる。だから、まだ仕事が終わったとは思っていないんです。毎日、これでいいのかって自分に問いながら叩いています」
仕上げの手順も、打つ順番も、都度試行錯誤。すべてがバラバラに見えながらも、ひとつの意志でつながっていく。その鎚音の奥に、職人の研ぎ澄まされた直感と調律された手技が息づいています。


また、「工芸の成果物って、突き詰めれば『翻訳』なんだと思うんです」と渡邉氏は語ります。
「形のないもの、つまり『思想』や『精神性』みたいなものって、本当はご先祖様から借りてきてるんですよね。それ自体は目に見えないし、言葉も時代が変わればどんどん古くなる。だけど、そういうものをどうやって今の人たちに通じるようにするか。その手段が『かたち』なんだと思います」
渡邉氏にとって工芸とは、受け継いだ価値観を「今の視点」で再解釈し、素材や工程、そしてプロダクトそのものを通してアウトプットしていく行為だと言います。
「だから、伝統をただ守るのではなくて、時には壊さなきゃいけない。翻訳って、原文どおりじゃ伝わらないときもあるじゃないですか。それと同じで、『伝えるために変える』っていう感覚が、今の工芸には必要なんです」
そうした哲学は、まさに今回のMR-Gとの取り組みにも通じます。伝統と現代、クラフトとテクノロジー。相反するようでいて、同じ「精神性」を宿すもの同士が出会ったとき、新たな翻訳が生まれる。
そしてそこには、渡邉氏ならではのチャレンジングな「叩き方」が、確かに刻まれているのです。

MR-GはG-SHOCKのなかでも、素材・構造・仕上げすべてにおいて「頂点」を追求したシリーズです。そこに日本の伝統技術が融合することは、単なる装飾ではなく、「ものづくりとは何か」を問い直す行為にほかなりません。
「伝統って、壊さなきゃ続かないと思うんです。同じことをずっとやっていたら、いずれ終わってしまう。だからこそ、G-SHOCKのように時代に合わせてアップデートしていく姿勢には共感します」
何百もの鎚目が刻まれたMR-Gのベゼル。そのひと打ちひと打ちは、渡邉和也氏が叩いた「思想」そのもの。
強さとは何か、美しさとは何か――
MR-Gが求め続けるその答えが、この時計には刻まれています。

これまでにない鎚起の技法を追求

渡邉氏の作業は、金属の表面に無数の鎚目を刻む緻密な工程。道具の刃先をこまめに調整しながら、手の感覚に集中してリズムを生み出していきます。たがねを右回りに打つか、左回りにするかも試行錯誤の末、最終的には右回りで安定した美しさにたどり着きました。
道具から試行錯誤し直した鎚起の技法

DAT55Gは極めて硬度が高く、通常の道具では歯が立たない素材です。渡邉氏は、その打ち込みに対応するため、たがねの角度や刃先の厚み、ハンマーの重さや柄の長さに至るまで、道具そのものを一つひとつ調整していきました。結果的に、DAT55G専用とも言える道具がいくつも生まれ、まさに素材との対話を繰り返しながら、理想の鎚目を実現していったのです。
アート制作も手掛ける渡邉氏の鎚起の未来

この作品は、縄文時代の火焔土器のオマージュとして制作されたアートピースです。渡邉氏は「工芸の成果物は、現代に向けて翻訳されるべきもの」と語ります。形のない価値を、いかに今の言葉と感性で伝えるか。伝統を受け継ぎながら、自らの表現で「現代の造形」へと昇華させる。そこにこそ、自身が挑むべき工芸の未来があると考えています。
Japanese Beauty: MRG-B5000 "Tsuiki" Limited Edition
Bluetooth® / MULTIBAND 6 / TOUGH SOLAR /
Premium Production Line